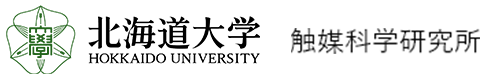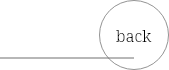研究

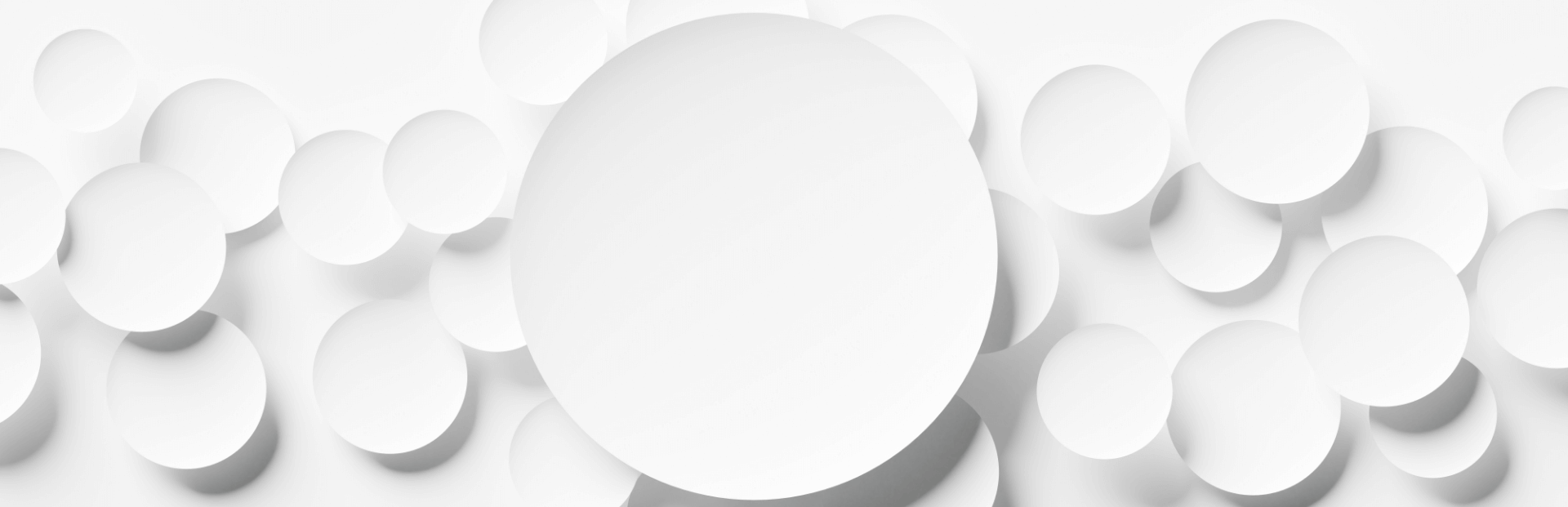
金ナノ粒子触媒による空気浄化とシンプルケミストリーの開拓
金にどのようなイメージを持っていますか? どのイメージの金も,輝いた姿を想像したと思います。この金属光沢は例え数千年であっても持続し、金は錆びない(参加しない)ことが、一般の方々でも科学者でも常識のことでした。つまり、金は化学的に非常に安定であり、酸素や水素などの分子と相互作用をしないと考えられていました。
首都大学東京(現 東京都立大学)名誉教授の春田正毅博士(故人)が、1987年に金ナノ粒子を触媒として用いるとCO酸化反応が、室温でも進行することを世界で初めて報告しました。また、同時期にカーディフ大学ではGraham Huthings教授が、アセチレンからの塩化ビニル合成において金ナノ粒子触媒の有効性を報告しました。それぞれの研究は独立してなされており、偶然にも新しい現象が同年に報告されました。触媒は、反応前後で変化しないこと学校で習ったと思いますが、反応中においては物質変換を促進するために、反応中間体と化学結合を形成します。金と化合物との相互作用はほぼ無いと考えられていたため、金が示した触媒作用の発現は驚きをもって受け止められました。金を5nm以下のサイズまでナノ粒子化することが、鍵でした.
バルク(塊)の金は化学的に不活性ですが、直径が2-5nmの非常に小さなナノ粒子になると、豊かな触媒作用を示します。これらの発表から40年近く経過し、触媒科学研究の世界では金ナノ粒子が触媒作用を持つことが常識となり、多くの触媒作用が見出されています。
村山教授は、2015年から春田名誉教授が主宰した金の化学研究センターに所属し、2017年から金の化学研究センターの主宰を任され研究を実施してきました。触媒科学研究所においても、金ナノ粒子触媒の研究を続けると共に、実用化研究の後押しをしています。
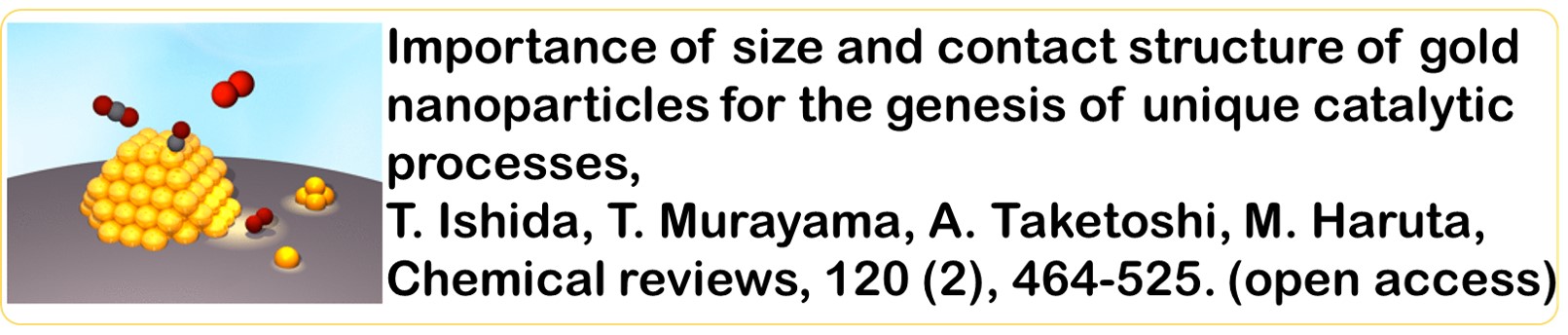
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00551